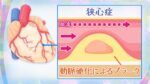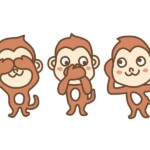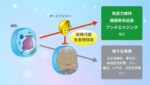腸内フローラを良い状態に保つのが非常に重要だと言われていて、それではと「乳酸菌」を多く摂ったり、「良いと言われる乳酸菌を買ってみたり」するのは私だけではないと思います。
ましてや「年齢とともに腸内環境は悪くなる」のが当たり前のようですし。
こんなグラフを見ると結構がっかりしてしまいます。(笑)

ただ「良い菌を多く摂ろう」なんて努力をしても「身体的に大きな変化は見られない」のね。ここが大問題。
でもま、「摂らないより摂ったほうが良いだろう」みたいなところで落ち着いて、良くわからないけれど「継続が大事だ」なんて信じ込もうとするのは私も同じ。
でも私は性格上、そういうのがあんまり好きじゃないんですよ。
だから自分なりに「自分の体を使った人体実験」を長らくやってきましたが、段々見えてきたことがあるので、それをまとめておこうと思いました。
まず、善玉菌を多く摂ることが重要と言われますが、何が善玉で何が悪玉、日和見菌なのかが良くわからないし、善玉菌を多く摂れば悪玉菌を駆逐するのかもわからない。だから「良いと言われるもの」をそのまま信じるしかない。
また「どうやって善玉菌を増やすのか」を考えた場合、「大量にとってもすぐに死滅する」ことは前から言われていて、でも「死骸も乳酸菌のエサとなる」のでそれでもOKだと。
でもそれって「悪玉菌の餌にもなっているはず」で、なんだか良くわかりませんよねぇ。
ただし、善玉菌は「糖分や食物繊維をエサとする」ようで、人の体に必要な諸々を生産する。悪玉菌は「タンパク質や脂肪分を主としつつ広範囲のエサを食べる」ようで、人の体に良くないものを生産するらしい。
では悪玉菌を減らすには「兵糧攻めにすれば良い」と考えられるわけですが、それは実際にある程度は効くらしい。つまり悪玉菌の餌になるようなものを食べなければ悪玉菌は減る。しかしそれは善玉菌が増えることを意味しない。ここは重要ですよね。
で、善玉菌も餌になるような物が入ってこなければどんどん減っていく。
では実際に「餌がなかった場合、どのぐらいのスピードで減っていくのか」を知りたいですよね。それがわかれば善玉菌、悪玉菌の「数のコントロールも可能」となりますから。
今現在、それを詳しく調べている最中で、その細かいデータを今は出すことはできませんが、【善玉菌はエサがないと1日で半減する。悪玉菌は25%減。その後、似たようなペースで減っていき、【1週間後、善玉菌は90%減。悪玉菌は65%減】の様な感じ。
これからも「善玉菌の面倒をちゃんとみないとならない」のがわかるし、それを怠ると「悪玉菌が多く生き残る」ようになる。これは断食を「善玉菌、悪玉菌の増減」という観点から見ると「良くない」のもわかりますね。
では「菜食主義者になればよいか」というと、そうでもないようで「悪玉菌のエサは腸内に十分ある」と言える様子。だからエサらしいものを食べなくても「悪玉菌は減るのが遅い」ということなんでしょう。つまり「善玉菌のエサを十分に摂って、善玉菌の優勢な状態を維持する事が大事」となる。
どちらにしても「餌が重要」なのは間違いがなくて、「良い乳酸菌+十分な餌」に主眼をおいてやってきました。
重要なのはエサ
ヨーグルトの自作をして気がつくことは「ほんの少しの種があれば無限に増やせる」と言っても良いことで、それと同じことが私達の体内でも起きているのでしょう。だから販売されている乳酸菌の摂取も「少量であっても良い」のかもしれない。餌ですが、これは基本的には「糖」「食物繊維」であるわけですが、砂糖を多く摂ることはしたくないし、そこで良く出てくるのが「難消化性デキストリン」でこれは多くの「機能性表示食品」にも含まれている。「食物繊維」が多いと。
「難消化性デキストリン」VS「イヌリン」
これらは乳酸菌のエサの「双璧」と言っても良いと私は思っていて、「エサ」「食物繊維」としての働きに重点を置くと「イヌリン」の方が良いと言われる。
これは「ヨーグルトの自作」でも良く話題に出ることだけれど、私も「イヌリンのほうが良い」と思っています。(詳細は今、ここには書きませんが調べればわかるはず)
ところがですね、イヌリンには大きな欠点がある。それは「溶けづらい」ことと「水分、湿気を吸収するとカチンカチンに固まる」という点。これって半端じゃなくて、「冷蔵庫や冷凍庫で保存」しても駄目だし、常温に放置すれば知らない間にカチンカチンになってしまう。だから一袋買っても「使い切るうちに使えなくなる」。当然、固まったものを割って使えば良いのだけれど、金槌で叩いても簡単に割れない強さがある。お湯には溶けるけれど、気持ちよく溶けるということもない。
「FOS=フラクトオリゴ糖」
ここで出てくるのが「FOS=フラクトオリゴ糖」で、これは扱いやすいと思うし、エサとしては「点滴のような効き目がある」のがわかっている。でも「入手」に関してはイヌリンや軟化性デキストリンの方が簡単。
人体実験をしていて気がついたことを書いておきますが、料理や飲み物のありとあらゆるものに私は「FOS=フラクトオリゴ糖」や「イヌリン」を入れて【体の変化】を観察しているのですが、「オリゴ糖を摂るとすぐにオナラが出る」。でもイヌリンの場合は6時間以上経ってからオナラが連発する」みたいな。でもこのオナラは「臭く無い」。(笑)
これは「ビフィズス菌や乳酸菌(きっと悪玉も含んでいる)」のエサになっているからなのは間違いがないのが実感できて面白い。
では「FOS=フラクトオリゴ糖」と「イヌリン」となぜそういう違いが出るのか。
イヌリンとFOS(フラクトオリゴ糖)の特性比較表
| 比較項目 | イヌリン (Inulin) | FOS (フラクトオリゴ糖) |
|---|---|---|
| 分類 | 水溶性食物繊維 (多糖類) | オリゴ糖 (少糖類) |
| 化学構造 | 果糖が10個以上 (長いもので60個以上) 繋がった 『長鎖』構造が主。 |
果糖が2〜9個ほど繋がった 『短鎖』構造。 |
| 主な供給源 | チコリの根、キクイモ、ごぼう、ニンニクなど。 | 玉ねぎ、ニンニク、バナナ、アスパラガスなど。サトウキビからの工業生産も多い。 |
| 腸内での発酵速度 | 緩やか(遅い) | 速い |
| 主な発酵場所 | 大腸の前半から、奥の部分(遠位結腸)まで、広範囲にわたる。 | 主に、大腸の入り口から前半(近位結腸)で速やかに消費される。 |
| 腸内細菌への影響 | 大腸全体にわたり、善玉菌を持続的かつ広範囲にサポートする。特に、大腸の奥で産生される酪酸の増加への貢献が期待される。 | 大腸の入り口付近で、ビフィズス菌などを集中的かつ速やかに増やす働きが期待される。 |
| 生理作用(ガス等) | 発酵が緩やかなため、ガス発生も穏やかで、腹部膨満感などの影響が出にくい傾向がある。 | 発酵が急激なため、ガスが発生しやすく、腹部膨満感やお腹の張りを感じやすい傾向がある。 |
| 味質 | ほぼ無味、無臭。 | 砂糖の30%〜50%程度の、上品な甘みがある。 |
| 物理的特性 | 水溶性。製品によっては、冷水にやや溶けにくい場合がある。食物繊維として便のかさを増す効果も。 | 水に非常によく溶ける。シロップ状の製品も多い。 |
| 適したアプローチ | 持続的・根本的な腸内環境のサポートを目指す場合に適する。穏やかな効果を好む場合に。 | 即効性・集中的なアプローチを試みたい場合に適する。摂取量にはより注意が必要。 |
要はFOS(フラクトオリゴ糖)の方が分解が早いということ。でも腸の入口で大半が消費されてしまい、大腸の奥までは届きづらい。でもイヌリンはその逆の働きをする。
これらの特性を考えると、私としては「優劣つけがたい」と思うし、「両方とも摂れば良い」と今は考えています。また乳酸菌にも「エサの分解の得手不得手がある」ようで、選ぶ乳酸菌によってエサも変えると違いが出てくる様子。
そして、乳酸菌ではない「伏兵」もかな~~り使えるのがわかってきた。
納豆菌が半端なく良い感じ
納豆菌は乳酸菌ではないけれど、昔からその「効能」は言われていて、私も納豆好きなことから「納豆菌を多く摂る、摂らない」ことを繰り返し、身体の変化を見ていました。
すると「乳酸菌ではわからない体の変化」が【納豆菌の場合は良くわかる】んですよ。それは「体調」というより【便通が非常に良くなる】という点。
私は便秘症でも下痢症でもありませんが、歳を取ってからは「スムーズさに欠ける」と感じていたのが納豆菌を多く摂ると非常に調子が良い。
一般的な乳酸菌・ビフィズス菌と納豆菌の特性比較表
| 比較項目 | 一般的な乳酸菌・ビフィズス菌 | 納豆菌 (Bacillus subtilis natto) |
|---|---|---|
| 体との関係(由来) | もともと人の腸内に住んでいる菌が中心。 | もともとは稲わらなどにいる自然界の菌。 |
| 腸内での振る舞い | 腸の中に住み着く(定住する)タイプもいる。 | 腸の中に住み着かない(定住しない)。数日間滞在した後、体の外に排出される「通過菌」。 |
| 酸への耐性 | 胃酸や胆汁酸に弱く、その多くが死滅してしまう。 | 酸や熱に驚異的に強い。 |
| 生存能力のメカニズム | 特別な耐性を持たない菌が多い。(一部、酸に強い菌株が製品化されている) | 「芽胞(がほう)」という硬い殻のような状態になり、過酷な環境から自分を守ることができる。 |
| 腸への生菌到達率 | 製品や菌株によるが、ごく一部しか生きて届かないとされている。 | 「芽胞」の防御力により、ほぼ100%が生きて腸まで届く。 |
| 酸素との関係 | 酸素が苦手(嫌気性)な菌が多い。 | 酸素がある環境を好む(好気性)。 |
私が最近、重要だと思うのは「納豆菌」で、納豆菌の凄さを改めてしっかり認識するのが良いと思いました。
納豆菌の体内における4つの主な働き
腸に住み着かない納豆菌ですが、体内を通過していく間に、体に良い様々な働きをします。
-
善玉菌を応援する
腸内にもともといるビフィズス菌などの善玉菌が、元気に増えるのを助けます。
-
悪玉菌を減らす
食中毒の原因になるような悪い菌が増えるのを抑える物質を作り出し、腸内環境を良い状態に整えます。
-
消化を助ける
納豆菌は、食べ物の消化を助ける様々な「酵素」を作り出します。これらの働きで、栄養の吸収が良くなるのをサポートします。
- 炭水化物を分解する酵素
- タンパク質を分解する酵素
- 脂肪を分解する酵素
-
体に必要なビタミンを作る
納豆菌の特に優れた働きの一つが、「ビタミンK2」を腸内で作り出すことです。 このビタミンK2は、カルシウムが骨にきちんと取り込まれるのを助け、血管で固まってしまう(動脈硬化の原因)のを防ぐ、非常に重要な役割を持っています。骨を健康に保つ上で、とても大切なビタミンです。
-----------
つまり「納豆菌」をいくら摂ってもそれが「体内で留まったり増えることはない」けれど、在住する善玉菌に取っては「非常に頼もしい援軍となる」ということじゃないでしょうか。
私が自分の体を使って人体実験をした結果としては、
○ 「摂取した乳酸菌が効果的に働いているのかどうかはわからない」
○ 「エサさえしっかり取っていればよいのかもしれない」(食物繊維を多く摂っていれば良い)
○ 注目すべきは「納豆菌」かもしれない。
これが今のところの私の結論で、結局、【納豆菌を重視する】のを基本として、「良い乳酸菌を摂り、エサ(糖類、食物繊維)を十分に摂る」てところでしょうか。
言葉を変えれば、【野菜を含めて食物繊維は十分に摂る。納豆はしっかり毎日食べる】ってことかと。多くのビフィズス菌や乳酸菌は【腸内に常在している】けれど、【納豆菌は常在しないけれど、非常に強い助っ人】みたいな関係でしょう。
だから「毎日摂るべき」は【乳酸菌ではなくて納豆】【善玉菌のエサになるもの】かもしれない。これが今日、一番書きたかったことです。
そして食物繊維の摂取を補うのに、「イヌリン」「FOS=フラクトオリゴ糖」「難消化性デキストリン」などを摂ればベターということかもね。ここでの注意点は「糖分を人体が消化吸収しないものを選ぶ」ということ。でも上の3種なら問題ない。
これが私が何年も掛けて、人体実験をしてわかったこと。
ただ、これで終わると私としてはまだまだ納得が行かないので、「本当に摂ったら良い乳酸菌を探す」ことをやめようとは思っておらず、それは乳酸菌に限らず、納豆菌と同じ様に「有用な菌」と呼ばれるものは「日本人の食生活」の中にいろいろありますから、「漬物」にしても【有用な菌を意識して摂る】のは良いと思っています。私はあまり「漬物」が好きではないのですが、「白菜漬け」なんてのは簡単にできるしバリバリ食べても美味しいので「常備したい」と思っています。
そして「趣味の乳酸菌」として私が注目しているのが「ロイテリ菌」で、これの効用はあちこちで言われているのに注目しています。
特にロイテリ菌の中でも【L. reuteri ATCC PTA 6475】という株に私は興味があって、これの培養(ヨーグルト作り)を計画中。乳酸菌にもいろいろあって、過去も現在も「話題になる乳酸菌」がありますが、私はこのL. reuteri ATCC PTA 6475ほど「面白そう」と思ったのもはありませんでした。でも培養はちょっと難しいようで、「ヤクルトの複製」みたいに簡単には行かない様子。
また有名なヤクルトの乳酸菌はラクチカゼイバチルス・カゼイ・シロタ株 (Lactobacillus casei strain Shirota)という株ですが、これも調べてみると本当に良い菌のようですので(シロタ博士には感謝)、培養(ヨーグルト作り)は始めています。
「そんな面倒なことを・・」と思うかもしれませんが、ヤクルトは家族も好きなんですが(風味が好きなだけ 笑)家族でガブガブ飲む(十分な量の乳酸菌を摂る)」となると結構な出費になるんですよ。でも培養すれば毎日ヤクルト20本分ぐらいの乳酸菌は簡単にメチャクチャ安く摂れる。また他の興味がある菌株もそれをしっかり摂ろうとすると、かなりの出費になる。まして「家族でしっかり摂る」なんてことになると簡単に毎月数万円の出費になってしまう。
正直なところ「本当に効いているのかわからないもの」に毎月、数万円をぶち込むことは私にはできない。
だから「自家培養をしよう」と思うわけです。培養自体、チャレンジの面白さもあって「やった~~\(^o^)/」という満足感もある。「密造酒作り、錬金術に成功した」ような感じでしょうか。(笑)
またヤクルトって「半端じゃない量の糖分」が入っている。それもまた「腸内のエサ」としているのだろうと思うけれど、難消化性の糖じゃないからヤクルトをガブガブ飲むんだら病気になる。(笑)
その他、興味がある乳酸菌には以下の様なものがあります。
ただ「培養が簡単ではない」のが普通で、「温度、酸度、酸素に弱い、雑菌に弱い」などそれぞれ特徴があって、「牛乳に種を入れてヨーグルトメーカーで放置すればオッケイ」みたいには行かないものばかり。
でも私は「低温調理」はもう10年以上の経験があるし、温度管理やその他の管理も「やれば出来る」と思っています。そもそも「体内で増える菌」なわけで、【そういう環境を作れば増やせる】はずで、そうじゃなかったら摂取しても意味がない。
問題は、「種菌をどう手に入れるか」。「菌株として販売されている」ものもあれば、「健康飲料」での入手しかできなかったり。錠剤やカプセルの中に入っているタイプのものは、それを使って培養する。
でもどうしようもないのは「目的の菌がちゃんと培養できているのかどうか」の確かめようがないこと。だから培養準備時の「殺菌」には何よりも気を使うし「他の菌が混入しないよう」な細心の注意が必要だと思っています。でもま、「ちゃんと培養できたときの状態」はわかりますから、出来上がりがおかしかったり変な色、匂いがあればすぐわかる。
世界的に注目されている主要なプロバイオティクス菌株リスト
カテゴリー1:『腸』の健康を主眼とする菌株
整腸作用など、プロバイオティクスの基本にして最重要の領域で活躍する菌株。
日本で特に有名な株
ビフィズス菌 BB536 (B. longum BB536)
所属: 森永乳業
概要: 日本を代表するビフィズス菌。半世紀以上の膨大な研究実績があり、整腸作用、免疫調整、アレルギー症状の緩和、感染症予防など、非常に幅広い機能性で知られる。安全性と実績で、世界的に高い評価を得ている。
ビフィズス菌 SP株 (B. breve Yakult)
所属: ヤクルト本社
概要: BB536と並ぶ、日本のビフィズス菌研究の双璧。特に、酸に強く、生きて腸まで届く能力が高いことで知られる。整腸作用に加え、肌の健康維持に関する研究も進んでいる。
LG21乳酸菌 (L. gasseri OLL2716)
所属: 明治
概要: 「胃で働く乳酸菌」として知られる菌株。ピロリ菌の活動を抑制する働きが大きな特徴。胃の健康を意識する層から、絶大な支持を得ている。
ガセリ菌SP株 (L. gasseri SBT2055)
所属: 雪印メグミルク
概要: 腸に長く留まる性質が確認されており、内臓脂肪を減らすのを助ける機能性表示食品として、日本で大きな市場を築いている。
海外で特に有名な株
ビフィズス菌 HN019™ (B. lactis HN019™)
所属: IFF (旧Danisco)
概要: 世界で最も広く研究されているビフィズス菌の一つ。整腸作用、特に大腸の通過時間(便通)を改善する効果で、非常に多くのエビデンスを持つ。免疫機能のサポートに関する研究も豊富。
乳酸菌 GG株 (LGG®) (L. rhamnosus GG)
所属: Chr. Hansen
概要: おそらく、世界で最も研究論文数が多い乳酸菌。下痢(特に抗生物質関連やウイルス性)の予防・改善において、圧倒的なエビデンスを持つ。免疫調整、アレルギー予防に関する研究でも知られる。
カテゴリー2:『免疫』と『アレルギー』に特化した菌株
免疫バランスの調整や、アレルギー症状の緩和に特化して選抜された菌株。
日本で特に有名な株
L-92乳酸菌 (L. acidophilus L-92)
所属: アサヒグループ食品
概要: アトピー性皮膚炎や、通年性アレルギー性鼻炎、花粉症といった、アレルギー症状の緩和に関する研究で、多くの実績を持つ。
プラズマ乳酸菌 (LC-Plasma) (L. lactis strain Plasma)
所属: キリンホールディングス
概要: 免疫細胞の司令塔である「pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)」を直接活性化するという、ユニークなメカニズムを持つ。これにより、免疫系全体の防御応答を強化するとされる。
カテゴリー3:『新しい領域』を探求する、次世代の菌株
従来の整腸作用を超え、全身の健康やQOL向上を目指す、最先端の研究対象。
海外で特に有名な株
ロイテリ菌 ATCC PTA 6475 (L. reuteri ATCC PTA 6475)
所属: BioGaia
概要: 抗炎症作用、ホルモンバランス(オキシトシン、テストステロン)への影響、骨の健康維持といった、全身のQOL(生活の質)に関わる、より高度な機能性が研究されている。
アッカーマンシア・ムシニフィラ (Akkermansia muciniphila)
概要: (乳酸菌ではない) 現在、腸内細菌研究の最先端で最も注目される細菌の一つ。腸の粘液(ムチン)を食べて増殖し、腸のバリア機能を強化する。肥満や2型糖尿病、代謝疾患の改善との関連が強く示唆されており、「次世代の有益菌」として製品化が競われている。
-----------
またヨーグルト作りもかなり奥が深くて、「2種類の違う種類を混ぜて培養する(サーモフィラス菌とブルガリア菌は共生関係にある)」ようにした方が良いとか、手に入る菌株でも、それを培養するには「スターター、補助となる他の菌株が必要」だったりするので、目的の菌株が手に入ればどうにかなるわけでもない。
でもヨーグルト作りを通して何百何千年の人類の歴史と叡智に触れるのも趣味として面白いと思っています。
また、今日、どうしてこの内容を書こうかと思ったのかですが、それは「AIの助け」で様々なことがわかってきたから。
今までの私の知識は「実践に裏付けされている」ものの、【断片的】だったり【根拠がわからない】ものばかりでした。当然「誤解」も山のようにあった。
でもAIのお陰で、プロがヨーグルト生産や培養の現場で何をしているのか、研究者はどんな研究をしているのか、そして半端じゃない数の論文や考察を横断的に調べることができました。ただし、私の様な「素人」の解説や考察、経験談は完全に無視しています。
そういう意味でも、私が書いた今日の内容は「私の理解、考え方でまとめたものでしかない」ですから、もし興味をお持ちの方がいらっしゃったら、是非ご自分でAIを駆使してお調べになるのが良いと思います。
でもま、雑談、バカっ話も好きな私ですから、どんな内容でもコメントを頂けると嬉しいです。
まずは「ヤクルト密造計画」から始めるのがよろしいかと。(笑)